不動産投資をある程度進めていくと、「このまま個人で買い続けて大丈夫か?」「法人名義に切り替えたほうが得なのでは?」という悩みに直面します。
名義の選び方ひとつで、節税効果、融資の通り方、相続対策まで大きく変わるのが不動産投資の特徴です。
今回は、投資ステージに応じた名義の使い分け方についてわかりやすく整理していきます。
目次
個人名義での不動産投資:メリットと注意点
✅ メリット
- 融資が通りやすい(給与所得がある場合)
サラリーマンや公務員などの安定収入があれば、属性評価が高く、最初の融資審査が通りやすい傾向があります。 - 手続きがシンプル
法人設立や会計処理の手間がなく、確定申告も比較的簡単に完結できます。副業レベルでの投資なら十分対応可能です。 - 費用がかからない
法人設立や維持に伴うコスト(登記・税理士報酬・均等割など)を回避できる点は、少額投資の段階では大きなメリットです。
⚠️ デメリット
- 税率が累進課税(最大45%)
所得が増えれば増えるほど、課税率が高くなる仕組み。利益が膨らむと税負担が重くなります。 - 経費にできる範囲が狭い
個人事業では、保険や役員報酬、退職金などを経費にしにくいため、節税対策の選択肢が限定されます。 - 相続・継承に弱い
個人名義の不動産は相続時に分割や名義変更が発生し、相続税やトラブルのリスクも高まります。
法人名義での不動産投資:メリットとデメリット
✅ メリット
- 法人税率が固定で低い(15%~23%)
所得税よりも税率が安定しているため、一定以上の利益を出す場合には節税効果が高まります。 - 家族に役員報酬を支払える
配偶者や子どもを役員にすることで、収益の分散ができ、所得税の圧縮や老後資金の準備も可能になります。 - 相続や事業承継がしやすい
法人の場合、資産の所有は会社。株式の譲渡という形でスムーズな継承ができ、相続トラブルの回避にもつながります。
⚠️ デメリット
- 初期コスト・維持コストが発生
設立登記、顧問税理士報酬、毎年の法人住民税(均等割)など、一定の固定費がかかります。 - 赤字でも納税義務あり
たとえ利益が出なくても、均等割の納税(地方税)が必須です。売上が安定するまでは負担になります。 - 融資が通りづらい(特に新設法人)
実績がない法人に対しては金融機関が慎重になるため、1棟目の購入には不向きなケースもあります。
融資面での比較:個人と法人どちらが有利?
融資戦略は、名義選びの中でも最も重要な観点の一つです。
| 比較項目 | 個人名義 | 法人名義 |
|---|---|---|
| 融資の通りやすさ | ◎(年収と勤務先で評価) | △(信用実績次第) |
| 審査対象 | 本人の属性と収入 | 法人の決算書と経営実績 |
| 金利 | 低金利が適用されやすい | やや高めになりやすい |
| 借入可能額 | 年収の倍率に制限あり | 実績次第でスケール可能 |
個人名義は「初めての投資家」に向いていますが、法人名義は「複数棟を所有して資産を拡大したい投資家」に適しています。
節税面での違い:収益規模に応じた判断を
節税効果を最大化するには、「どれだけ利益が出るか」がポイントです。
- 年間利益が300~400万円以下の場合は、個人の方が手取りが多くなる場合があります。
- 年間利益が500万円以上になると、法人化による節税メリットが見えてきます。
- 将来的に退職金の積立や保険活用をしたい場合も法人の方が柔軟です。
ただし、法人化に伴うコストも考慮しなければなりません。
相続・事業承継の観点で考える法人化の意義
将来の資産継承を見据えるなら、法人名義は非常に有利です。
- 株式での継承が可能なため、不動産ごとの名義変更や分割の手間が不要
- 相続税の評価額も下げられるスキームを活用しやすい
- 相続後の賃貸経営も、法人単位でスムーズに継続できる
相続対策としての法人化は、“長期視点の戦略”として有効です。
名義選びの鉄則:「目的とステージ」で判断を
不動産投資における名義選びには、万人に共通の「正解」は存在しません。
大切なのは、以下のような視点から判断することです:
- 投資規模・収益目標に見合った税務設計ができているか?
- 5年後、10年後の出口戦略や相続まで考えられているか?
- 投資のステージ(1棟目/複数棟/法人化のタイミング)に適しているか?
名義は「現状」で選ぶものではなく、「未来の戦略」に基づいて選ぶものです。
まとめ:最初は個人、将来的に法人という選択肢も
不動産投資の初期段階では、まず個人名義でスタートし、規模が拡大した段階で法人を設立する、という“段階的戦略”も有効です。
重要なのは、節税・融資・相続などの観点を踏まえ、自分にとって最適なステージで名義変更を検討することです。
法人化を検討する際は、税理士や融資の専門家と連携して、最適なスキームを設計していきましょう。
📢 次回予告:
「融資を引き出すコツと金融機関との付き合い方」
“選ばれる投資家”になるための金融機関対応術をお届けします!

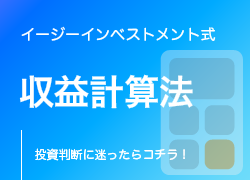
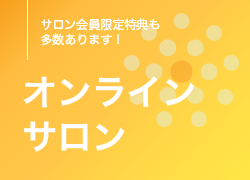
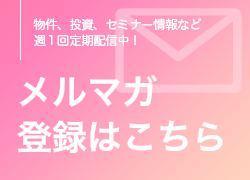
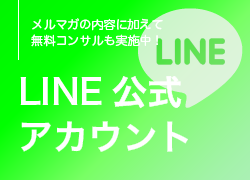


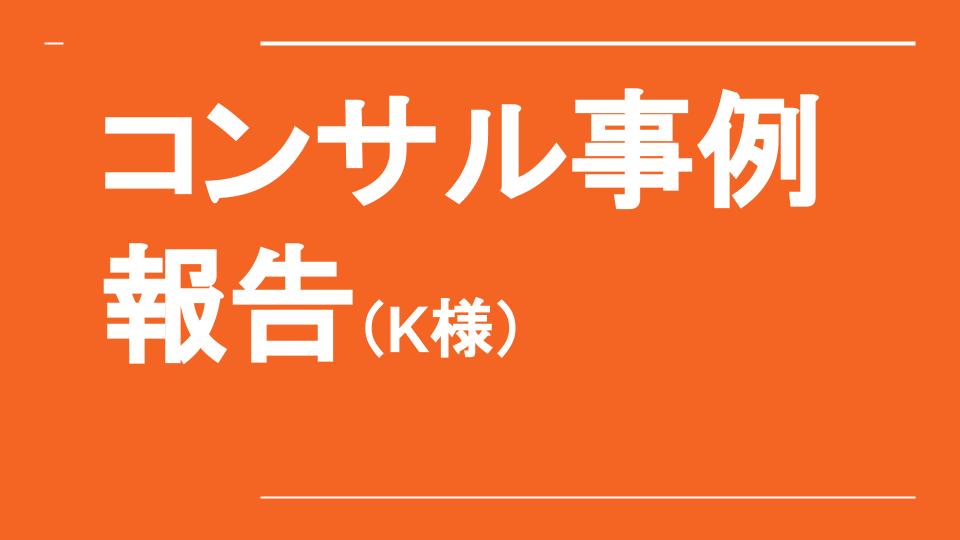





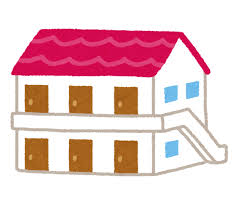





コメントを残す